
シリーズでお伝えしている復帰50の物語。今回は、「祖国復帰運動」が盛り上がる当時の沖縄において、その運動とは別の角度から「復帰」への思想に一石を投じた人物がいました。その思想は、いわゆる「反復帰論」として、多くの人に知られることになりました。
復帰50年を迎えるいま、改めて、当時伝えようとした「復帰」への問いかけを見つめなおします。
新川明さん「一般に反復帰論というのはつまり復帰に反対する、当時、復帰を求めて沖縄が全体的に盛り上がっていた復帰運動に対する、反対運動的な考え方と理解されてるんじゃないかと思います。そこに大きな誤解があるんです。日本から離別して琉球独立国つくると、また同じ小さなミニジャパンみたいな国家をつくる、これでは何の意味もないわけです」
新川明さん。沖縄タイムスの記者として、各地をまわった経験をもとに八重山の島々の生活を書き記した「新南島風土記」や沖縄の自立について書いた「反国家の兇区」、沖縄戦の悲惨さを絵本であらわした「りゅう子の白い旗」など、様々な角度から沖縄を見つめ、伝えてきました。
復帰運動が熱を帯びていた1960年代、日本を祖国とみなして突き進むウチナーンチュに対して、新川さんは大きな疑問を抱いていました。

新川明さん「なぜあの日本が祖国かと、祖国ではないだろうという気持ちがあるわけで。ウチナーンチュの祖国というのは琉球国じゃないかと。かつての琉球王国が祖国であって、そしたら、琉球国復帰運動とすべきじゃないかと」
それは政治運動などではなく、個々人が持つ思想のあり方であり、沖縄の歴史から紐解くウチナーンチュの原点と日本という国家に抱く幻想を乗り越えようとする復帰へ問いかけでした。
新川明さん「なぜ(本土と)異なった歴史を生きてきたウチナーンチュが、そして、戦前ひどい目にあったウチナーンチュが、なぜ再び自分から進んでその国の中に入っていくのか。なぜ、そうなるのか、おかしいんじゃないかと問い続けたのが、僕にとっての反復帰論なんです」
新川さんの故郷である西原町の図書館には、9000点を超える資料が所蔵された「新川明文庫」があります。
ここに新川さんの復帰への問いかけが世に広がるキッカケとなった本がおさめられていました。当時沖縄タイムスで発行されていた雑誌、「新沖縄文学」です。
復帰運動の背景として「米軍統治に対する抵抗」と、「新しい憲法のもとに生まれ変わった日本への憧れ」があったと当時の沖縄の状況を振り返っています。
新川明さん「敗戦して生まれ変わって、そこで生まれた日本国憲法への憧れと、米軍のひどい弾圧と抑制と人権を無視した、それに対しての抵抗と、そういった社会から抜け出したいと言う気持ちが復帰運動につながって生まれた」
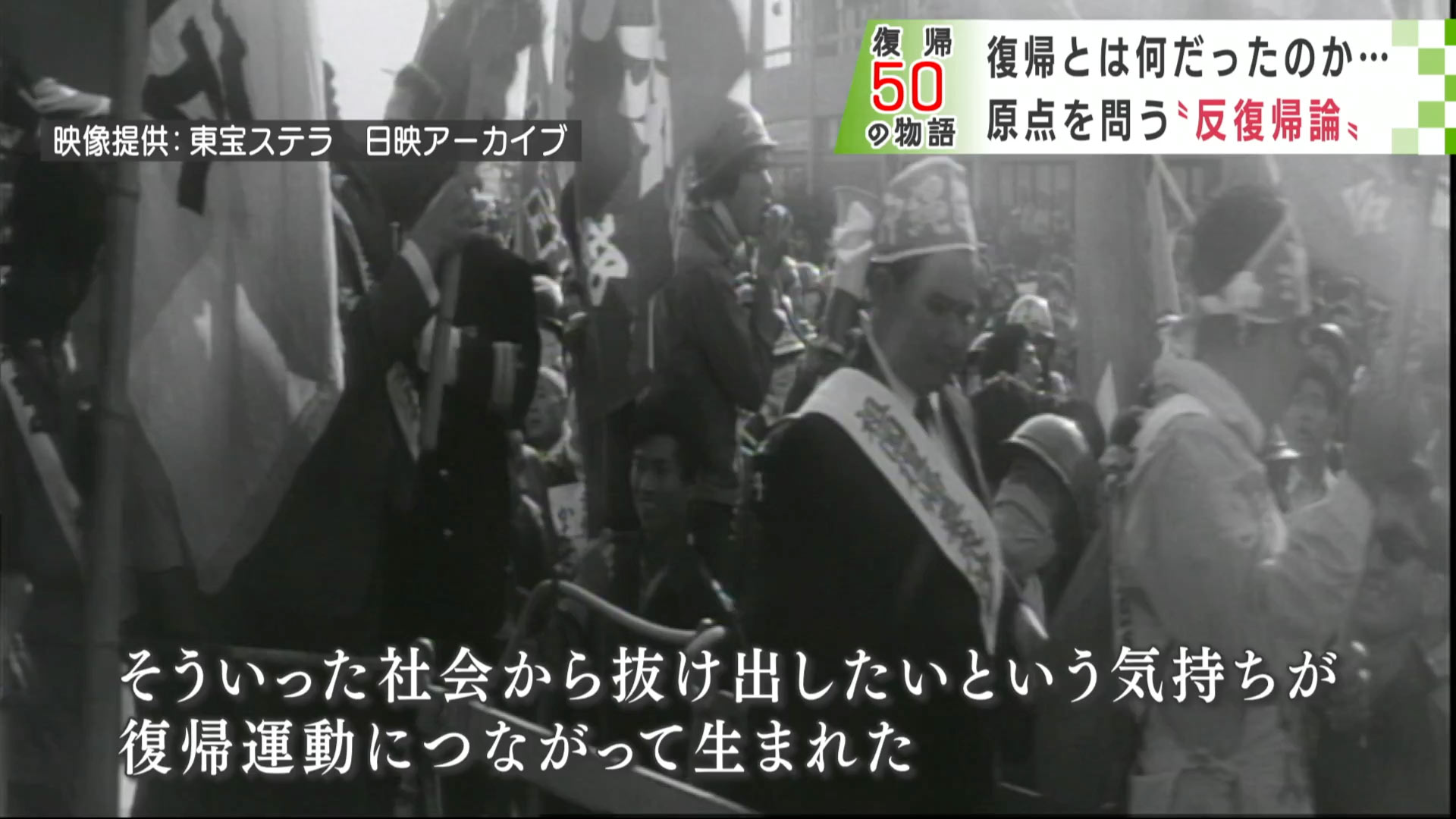
しかし、日本という「国家」に取り込まれていくことは、沖縄が政府の思い通りに扱われることになるのではないか、そこに沖縄の自立はあるのかという危惧を抱いていました。
新川明さん「復帰から50年経った今の沖縄が直面している状況。沖縄の民意について一顧だにしないやり方がずっと続いている。象徴的に言えば、辺野古の問題にしても、あれだけ県民投票も含めて、反対の意思表示しても、全くそんなものを無視して、進めていくだけでなくて、奄美大島を含めて、沖縄本島それから、宮古・八重山と琉球弧、全体を米国と一緒になって、軍事要塞化していく、そういう状況に、ここまでなるとは、その当時はもちろん思わなかったけど」
本土復帰から半世紀を迎えた沖縄の現状に対し、新川さんの胸に祝福ムードの気持ちはありません。
新川明さん「だいたい復帰50年って言って、お祝いしようとする動きが大きいでしょ。県当自体が、ヤマト政府と一緒になってお祝いしようなんて考えているのが現実だから。そういう意味では、なんか妙にむなしいような感じが先に立ちます」
今も残る復帰と日本に対する幻想を乗り越えない限り、「沖縄が自立することはない」といいます。
新川明さん「かつての復帰運動の中で見られた、日本に対する憧れていた、そして幻想を持っていた、僕はそれに対して復帰幻想という言葉で表現したし、日本の国家に対する幻想については祖国幻想という言葉で表現して、いろいろ書きました。そして、復帰運動というものを作り出していった、うちなーんちゅの精神の働きというもの。その復帰思想の根っこの方は、50年経っても消えない。だから、それを乗り越えていかない限りは、沖縄の自立というのは望めない」
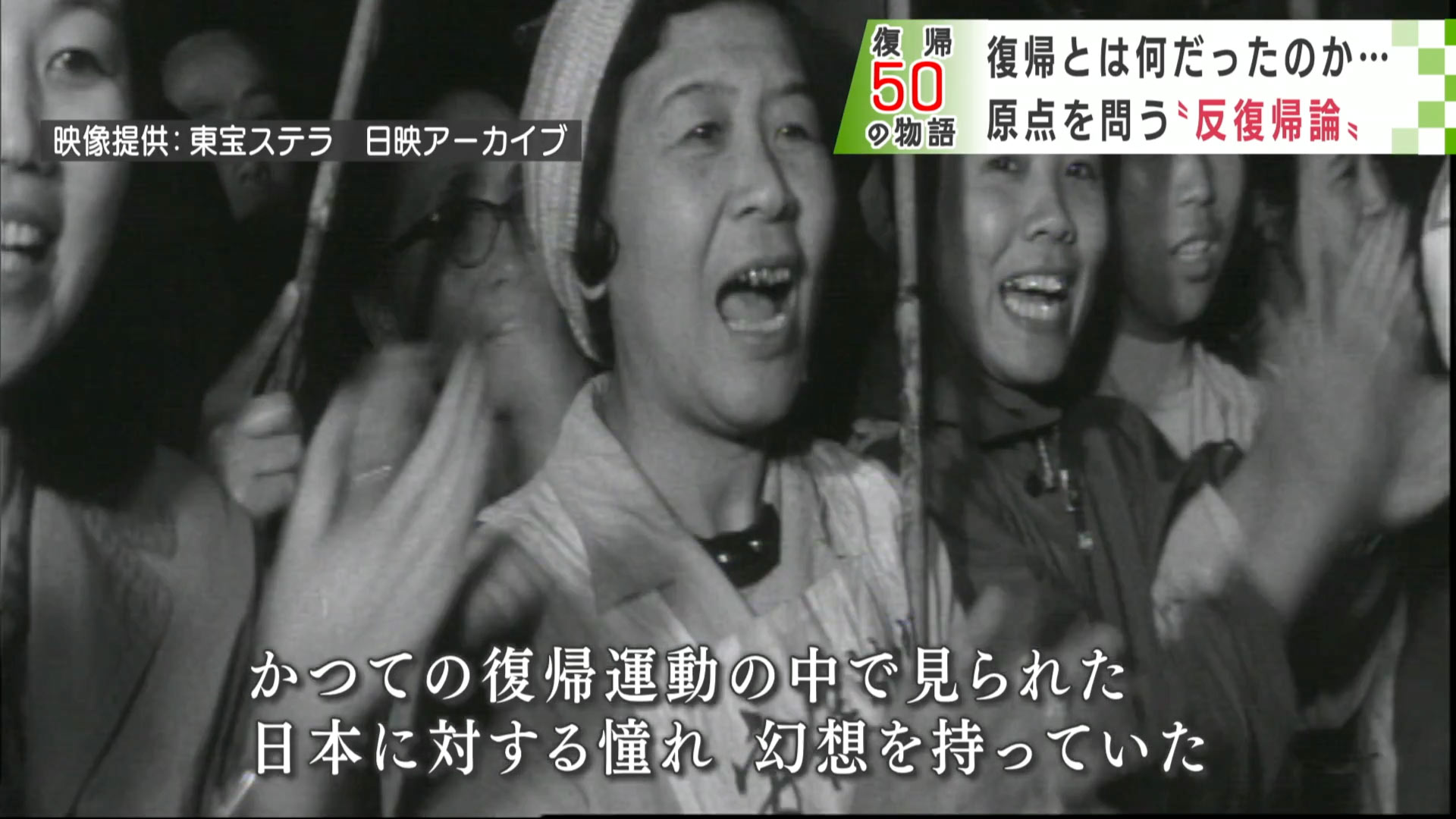
復帰から50年の時を経て、当時、新川さんが示した「復帰」への問いかけは、今なお、ウチナーンチュへと向けられて続けています。
